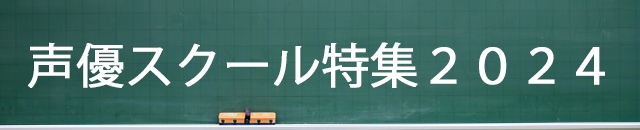若いうちからさまざまなものを見て
自分の中の引き出しを増やしておくこと
よく「いろいろな役をどうやって演じ分けているんですか?」と聞かれるんですが、実際にはそんなに演じ分けられるはずがない。画面には違う俳優さんやキャラクターが映っているから、きちんと演じ分けができているように、見ている人が錯覚を起こしているに過ぎないんです。ただ、もしコツがあるのだとしたら、リズムです。呼吸のリズムが一人ひとり違うんです。たとえばウディ・アレンとシルベスター・スタローンは、呼吸のリズムが違うからしゃべり方もまったく違う。ウディ・アレンが早口で軽くしゃべるのに対して、スタローンは腹の底からの深い呼吸で獣のような声を出すんです。
こう簡単に説明していますが、僕自身も初めてスタローンの吹き替えをすることになったときは戸惑いました。「どうして僕を選んだんですか?」ってプロデューサーに聞きに行ったくらいですが、「まぁいいから演じてよ」って軽く流されました。そう言われてもどう演じていいかわからなかったもので、仕方がないから声のトーンだけは下げようと思ったんです。それで海岸に出かけて、海に向かって浄瑠璃を長時間演じて、喉をガサガサに枯らしてから収録に臨みました。ウディ・アレンを演じるときは、軽妙な語り口が特徴だからと、収録前に早口言葉を練習したりしてね。どんな役を演じるにしても、そういう努力はしていますよ。あえて「こんなことをしました」とはあまり語らないけどね。当時は声優の数も少なかったから、声のトーンを上げたり下げたりしてなんとか演じ分けようとしているヤツがいれば、「とりあえずコイツにやらせてみよう」と何の役でも振られちゃったんです。
また、映像だけじゃなくて脚本家の力も大きいと思うんですよ。たとえば小池朝雄さんが演じた『刑事コロンボ』なんて、声だけを取り上げたら本人そのまんまなんです。でも「ウチのカミサンがね」というセリフを言うと、もうコロンボにしか聞こえない。「ウチのカミサンがね」なんてセリフ、日常生活じゃまず出てこない言葉ですよ。それだけのインパクトがある台本だったからこそ世間に広まって、みんなコロンボからあの声が聞こえるのが当然だと思うようになっちゃった。ピーター・フォーク自身が出てきてしゃべったら、「声が違う」って苦情が来たっていう笑い話があるくらいです。
今の脚本家さんは、直訳してしまうんです。原文を正確に訳するのが仕事になっちゃってる。これは声優も同じです。正確に原文を訳すこと、イメージどおりにキャラクターを演じることは、プロの仕事ではありません。そこに自分なりの色をつけてこそ、誰もが「この役はこの人」と思うような印象的な仕事ができるんです。翻訳は自分のもっているボキャブラリーの中でしかできないし、演技は自分のもっている引き出しの中でしかできません。だからこそ、若い人たちにはさまざまなものを見て、見聞を広めてほしいですね。そうして培ったものを自分の引き出しの中に入れておいて、何かあったときにパッと使えるようにしておくことです。手品師のようにね。
技術が拙い時代だったからこそたくさんの経験を積めた
昔はまだ技術も設備も拙かったから、収録現場ではいろいろなことがありました。今のように事前にリハーサルビデオをもらえるなんてことはなかったので、収録前日にキャスト陣が集まってフィルムを1回通して見てリハーサルをしていたんです。
『チャタレイ夫人の恋人』という映画にはベッドシーンがあるんですが、ヒロインを演じることになった女優さんがアフレコに慣れていなくて、前日リハーサルのときに「ベッドシーンはどうするんですか?」って小声で聞いてきたんです。僕はいたずら心を起こして、「明日はスタジオにベッドが置いてあるから大丈夫だよ」と冗談を言ったら、その女優さん、泣きながらスタジオを飛び出していって「こんな仕事できません!」って事務所に電話していました(笑)。
『コンバット!』という海外ドラマシリーズでは、収録の前日に嵐が来てスタジオが水没したことがありました。ミキシングルームはちょっと高いところにあったので、機材は被害をまぬがれたんですが、スタジオ内には水がたまっちゃってる。でも、代わりのスタジオが見つからなかったらしく、収録に行ってみたらディレクターさんがみんなに長靴を配っているんです。当時のスタジオは1本のマイクですべて収録していたので、キャストはみんな入れ替わり立ち替わりそのマイクに向かって歩いていくわけですよ。するとジャブジャブ音がする。でも放映時間が翌日に迫っていて間に合わないっていうことで、そのまま収録しました。皮肉なことに『砂漠の将軍』っていうエピソードだったのに、なぜか水音がするというおかしなことになっていました(笑)。そういうことを平気でやっていた時代だったんです。
僕はそんな時代に声優を始められて、ある意味ラッキーだったと思います。声優ではなく「アテ師」なんて侮蔑的な言葉で呼ばれていたりもしましたが、そのお陰でさまざまな作品に参加できたし、その中で試行錯誤することで演技力を養うことができたんです。あの頃の自分から見ると、今は声優になりたいっていう人が山ほどいて、声優になるための養成所がこんなにたくさんあるなんて、考えもしなかった状況になりました。でも今、僕がデビューしたとしたら、同じ年月で今の場所までたどり着ける自信がありません。
役者というのは、必ずしもうまい人が成功するわけじゃないんです。チャンスが巡ってくるか、そのチャンスをつかめるのかが勝負で、ときには、もっとうまい人がいるのに、巡り合わせで役がとれてしまうこともある。だからこそ、チャンスが巡ってきたときには必ずつかめるくらいの実力を養っておかなければと思います。