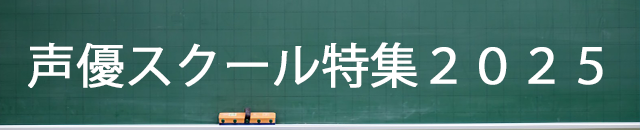本当はマグロ漁船に乗るつもりだった
本当はマグロ漁船に乗るつもりだった
父・大塚周夫さんに続き、親子二代で声優という職業に就いた大塚明夫さん。アニメーションだけでなく、スティーヴン・セガール、ニコラス・ケイジなどの洋画吹き替えでも活躍されています。大塚さんの声優道を振り返りながら、声優としての心得やヒントを教えてもらいました。前後編の2回に分けてお届けする前編では、声優になるまでのお話、またお父様である大塚周夫さんの存在について伺いました。
大学中退後トラック運転手に
もともと僕は声優になるつもりはなかったんです。大学中退後、僕はトラックの運転手をしていました。人生の選択肢が削れていって、残ったものがトラック運転手の道。バイト先で正社員になって、転々として。本当はマグロ漁業の船に乗ろうと思っていたんですけど、歯の治療が間に合わなくてね(笑)。その間に乗る予定の船が座礁してしまって乗れなかったんです。でも、そっちの方向に進んでも道はないなとも考えていました。今思えばダメダメな若造だったんです。
そんなとき、同級生の女の子に会ってね。その子の彼氏はある劇団の準劇団員だったんですけど、その女の子が「男の人は夢があるほうがいい」と。その言葉が強く残ったんですよ。それで僕も歌でも歌うか、芝居でもしようか、って。でも楽器はできないから、とりあえず芝居か──それくらい安直だったんです。失うものは何もないという状態だったので、そこは強いですよね。何の迷いもなく、捲土重来、乾坤一擲で役者の道に飛び込みました。
1983年、23歳の頃に文学座附属演劇研究所の門を叩くことになります。文学座は松田優作さん、中村雅俊さん、渡辺 徹さんなどを輩出していて、あちこちからいろいろな人が集まっていました。今では考えられないほどの受験者がいたと思います。当時は肉体訓練のようなものはなく、エチュードや戯曲が中心。文学座での毎日はとにかく楽しかったです。つらいことはいっさいなかった。それまで男性ばかりの殺風景な生活を送ってきたものですから(笑)、若い男女が一緒になって教室で学ぶということは、ものすごくまぶしいものに感じていました。まさに青春時代ですね。
でもそんな楽しい日々も続くわけではなく、入所して1年後に「卒業です」と言われて、それでおしまい(笑)。卒業後はこまつ座に入団。その年の秋、新橋演舞場のお芝居に出ることができて、初めて職業俳優としてのギャラをいただきました。「初めて稼いだお金だ」というドラマティックなものはありませんでした。「もっと稼がないとな」と。
当時は夢中で芝居をしたり、バイトをしたり。目の前の本とただひたすら格闘していました。そんなある日、親父から「お前、声の仕事やってみる?」と声をかけられ、二つ返事で引き受けました。やっと親父が「いけるだろう」と思ってくれたんでしょうね。今思えば、声を掛けるタイミングを見計らっていたようにも思います。
父・大塚周夫の存在
父が亡くなって6年たちます。僕にとって父は間違いなく大きな存在でした。ただ語るとなると難しいものがあります。幼少期、テレビから父の声がすると、すぐにわかりましたし、出演作を見ることもありました。でも父が自宅にいることは少なかったですし、仕事している様子を見たこともない。どうやって生きていたのか、僕自身は知る由もなかったんです。
自分がいざ演劇をやるとなった時期は、父はほぼ演劇をしていませんでした。僕が23歳の時に父が53歳。こまつ座にいた時に、いろいろな役者を間近で見たものだから、自分の親父が……語弊があるかもしれないですけど、当時、そこまですごい役者とは思えなかったんです。声の仕事をするようになって、初めて父・大塚周夫の凄みを感じました。どういう覚悟を持って役者として生きてきたのか、やっとわかったんです。
役者・大塚周夫の芸道父は役者を始めた当初、劇団東芸に所属していました。劇団東芸は、野沢雅子さん、富田耕生さんや森山周一郎さんなどがいた大きな劇団。舞台では主役に抜擢されることもあったらしいんですが……そこを辞めて、小沢昭一さんが立ち上げた俳優小劇場の研究生になったんです。養成所生の1年間は仕事をしてはいけないという決まりがあって、お袋が泣いていたことを覚えています。そりゃ泣きますよね(苦笑)。2歳、6歳の子どもがいるのに仕事ができない。つまりお金が入ってこないわけですから。それでも父は「自分は今、これをやらなければいけない」と覚悟を決めてその場所にいったんだなと。役者としてすごいことです。自分が同じ道を辿って父の背中が見えたとき、どれだけの信念を持って役者をしていたかがわかり、父を誇りに思いました。それを理解してからは、父の言葉の重みを感じるようになりましたね。
これは余談ですが……僕には弟がいるんですが、弟はこの道に進まなかったので、弟も父も「二人になると何を話していいかわからない」とよく僕に話していました。家族のなかで僕だけが、仕事を介してコミュニケーションを取れていたんです。それは良かったなと思っています。
撮影/石田 潤 ヘアメイク/addmix BG 取材・文/逆井マリ
声優としての転機、また声優として生きるためのヒントなどについて語ったインタビュー後編はこちらから