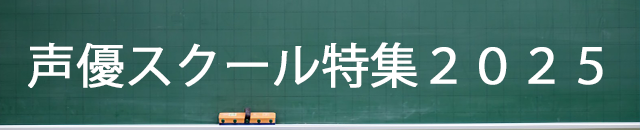僕は神経質かと思えば大胆なところもある
そうやって自分自身を観察することが重要
声優を目指す人や後輩から、さまざまな役を演じ分けるコツを聞かれることがあります。でも、演じ分けなんて一足飛びにできることじゃないんです。もしコツがあるとしたら、役者の目でものを見続けることですね。おかげ様で僕は子役時代からそういう目を養うという経験を積ませてもらえましたが、日常生活は役者にとって題材の宝庫なんです。さまざまな人と接した経験、今までに見てきたもの、それが役を演じるときの素材になるんです。何か役をいただいたときに、自分の中にため込んできた引き出しの中から、「これはあのときに会ったあの人に似ている」「あのときに経験した感情だ」というような要素を引っ張り出して、すり合わせをすることで演技が出来上がっていくんですね。役者の目で物事を観察して、引き出しの中に素材をたくさん積み上げていく、それが大切なんじゃないかと僕は思います。
あと、同じ役者の目で自分自身を観察することも必要です。誰でも、仕事中に見せる表情とプライベートでの表情は違います。また、親に対してだったり、友達に対してだったり、接する相手によっても変わってきます。それにプラスして、そのときの機嫌によってもさまざまに変化します。
人間の表情って、いろいろな要素が絡み合って、無限に変化していくじゃないですか。みんなそういうさまざまな面をもっていますけど、他人のすべての面を観察することはできません。でも、自分自身なら常に観察できますからね(笑)。
僕はちまちまとした細かい作業が好きな神経質なところがありますが、舞台で体を張って笑わせるような大胆な一面もありますし、涙もろいくせに冷徹な一面もあるんです。そういう、一見相反するような感情も、人間の中にはちゃんと同居しているんです。自分にとって嫌な一面だから見たくないと目を伏せるのではなく、役の中に落とし込んでいく。
役者というのは、私生活をどう生きているのか、どういう目でものを見ているのかを、常に問われている職業だと思います。
表現者にいちばん必要なのは「好き」という気持ち
役者にとっていちばん大切なのは、演じることが好きかどうかですね。役者を目指している人と接したときには必ず、「演じることが本当に好き? 好きといっても、いちばん好きじゃないと続けられないからね」と聞きますね。「好き」だったら、その「好き」をもっと育ててほしい。「好き」がどんどん大きく育っていくと、それがエンジンを動かしてくれる燃料になるんです。その循環ができてないと、何を言っても何も積み上がっていかないんです。
たとえば滑舌なんて、訓練すれば誰でもできるようになるんです。100回やってできる人もいれば、1万回やらなくちゃできない人もいますが、最終的には誰でも必ずできます。でも、好きじゃなければ訓練なんて努力をしたいとも思わないでしょう。そして、できるようになれば、もっと頑張ろうと思えるようになる。だからこそ、好きでいることがいちばん大切なんです。もちろん僕だって、忙しすぎて「もうしゃべりたくない」「もう声なんか出ねぇよ」と思うことはあります。でも、しばらくぼーっとして落ち着いてから、また改めて考えると「やっぱり演技が好きだ」というところに戻っちゃうんです。本気で追求しているからこそ、向上心があるからこそ嫌になる。僕はそう思っています。小学4年から「好き」というだけでここまで歩いてきましたが、今のほうが1000倍以上好きだと胸を張って言えます。
あと表現者には、二つの柱があるんです。一つの柱が発声や滑舌といったスキルだとすると、もう一つの柱は感受性です。その2本の柱を等しく育てていかないと、表現者にはなれないと思っています。スキルはやればやっただけ結果がついてきますが、感受性というのはその人の生き様なんです。どうやったら育てられるというものでもないし、結果が出るものでもありません。役者としての目を意識して、積み上げていくしかないんです。役者をしていると、犯罪者の役を演じることもあれば、宇宙人や神様を演じることもある。日常生活で積み上げたものだけでは演じられない役が来ることもあるんです。日常生活だけでなく、映画、小説、本、マンガなど、すべてのものを役者としての目で経験することですね。でも、逆に言うとこの2本の柱が育っていけば、個性のある素晴らしい役者になれるんです。
僕も長いことこの業界にいますが、年齢を重ねれば重ねるほど、その先で表現したいものが出てくるんです。見た目や声質など、この年齢だからこそできることっていうのもあります。今でも新しいことにいろいろ挑戦し続けていますが、まだやりたいことが全部できているわけではないんです。頭の中にはすでに2~3年先のビジョンがあるんですが、「そこまで考えたらこういうこともやっておきたい」「こんなことにも挑戦したい」と考えちゃうんですよ。本当にこの仕事には終わりがないと思いますね。
(2011年インタビュー)